「よー、チャチャチャン、チャチャチャン、チャチャチャン、チャン」
歓送迎会や宴会の最後に手をうち、こんなかけ声をみんなでかけたことはありませんか?
宴会の最後にとり行われる一本締めとよばれる挨拶について、ここではその類似の挨拶の紹介と、一本締めの場面やシチュエーション、そして一本締めでつかえる挨拶のことばを例にあげてみました。
目次
一本締めとは?
一本締めとは日本の風習の一つで、「手締め」とか「手打ち」とよばれ、かけ声にあわせて手を打つことです。

たとえば冠婚葬祭や歓送迎会、また商談や株主総会などでおなじみですが、物事が無事に終わったことを祝いとり行われます。
正式な一本締めとは、手を10回叩く方法です。
「よー、パパパン、パパパン、パパパン、パン」3回、3回、3回、1回の計10回、かけ声にあわせて手を打ちます。10回の意味は「九」という字に「一」をつける。すなわち「丸」という字。丸く会がおさまったことに感謝する意味が込まれています。
類似の行為に一丁締めという行為がありますが、これはかけ声にあわせて手を1回打つ行為。「よー、パン!」です。
一本締めを簡単にしたもので、おおげさにできない会場など、周囲へ配慮が必要なときに一本締めの簡略されたこの形式がつかわれます。一本締めを略したものなので、ホテルや大きな会場や、盛大な席ではつかわれません。
会社によっては、一本締めと一丁締めを間違って覚えているところもありますが、その辺りは正しい知識がどうのこうの言わず、会社に合わせるほうが無難でしょう。
手締めは一本締めが正式ですが、このほか、一本締めのかけ声と手打ちを3回繰り返して行う三本締めという行為があります。三本締めも一本締めと同様に正式な手締めです。
たとえば、舞台の終了時に舞台上からその関係の代表者が上手そして下手、最後に真ん中の観客にお礼の挨拶に三本締めをします。主催者に、来賓者に、そして会自体にむけた感謝とお礼の意味があるといわれています。歌舞伎の会場でもよくかけられる挨拶です。
一本締めの場面やシチュエーション
一本締めもしくは三本締めは、その会の最後に、司会者、運営者、幹事を携わった人や指名を受けた人が、会をお開きにするタイミングをはかり、出席者に感謝の言葉とともに締めをかざるときに行います。
その場面やシチュエーションは、宴会を一区切りさせる時や早々に退会したい人への配慮、またその宴会や会合に一区切りつける時におこなわれる「中締め」。そして、会が完全にお開きに近づいた時に最後までやり遂げたという気持ちをこめて、会を終える時の「締め」の場面の、主に2つです。
中締めでは、そのあと、散会するためではないので、一本締めや三本締めのあとしばらく歓談の時間ももたれ、二次会の案内も同時にされることがほとんどです。
一本締めまたは三本締めでの挨拶の例

商談や株式総会などの場合は、ベテランの運営者からの決まり文句で手締めが行われますが、たとえば結婚式や歓送迎会など、自分の身近で締めの場面を取り仕切ることになった場合は、こんな言葉を用いて、一本締めや三本締めを決めるとよいでしょう。
以下、一本締め(三本締め)での挨拶の例を紹介しておきます。
中締めの場合
「ではそろそろ会場の時間も迫ってまいりましたので、いったん締めさせていただきます。本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます。会を祝し、一本締めでいったん会をしめさせていただきます。それではみなさま御手を拝借ねがいます」
締めの場合
「ご指名に預かりました(名前)です。本日は楽しい時間を皆さま共に送りことができまして大変うれしい思いです。今日お集まりくださいました皆様の健康(発展)を願い、僭越ではございますが、一本締め(三本締め)で会を締めさせていただきます。皆様ご起立していただきまして、御手を拝借、お願いします」
まとめ
いかがでしたか?
気持ちよく宴会や会合をお開きにするために用いられてきた日本の風習のひとつ一本締め(三本締め)。
「終わりよければすべてよし」ということわざがあるように、最後をかざる大役がまわってきたときは、その場面をよんで、タイミングよく皆さんに御手を拝借してもらえるといいですね。






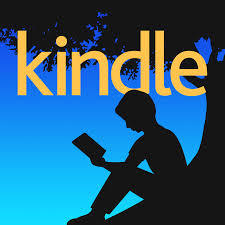



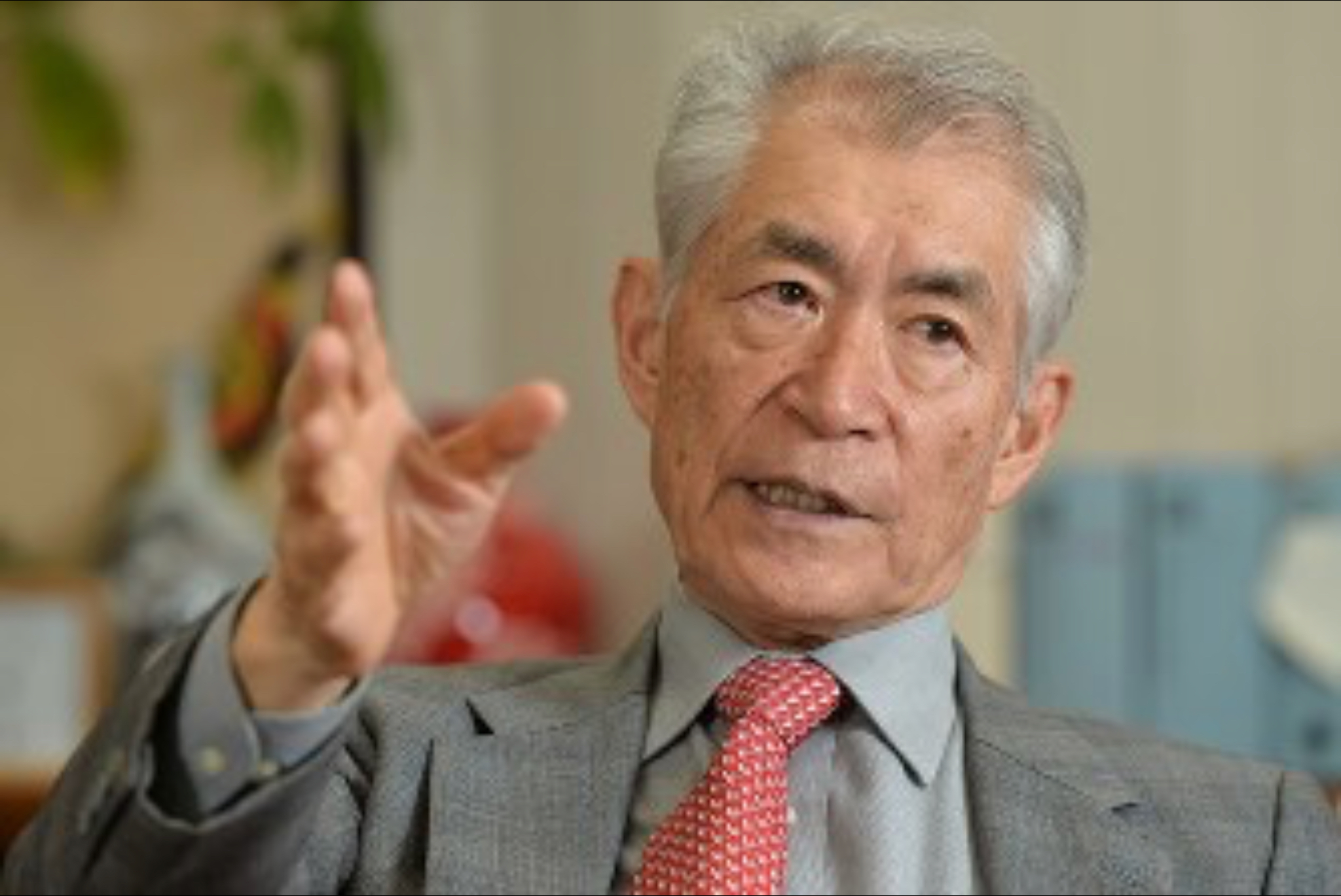




コメントを残す